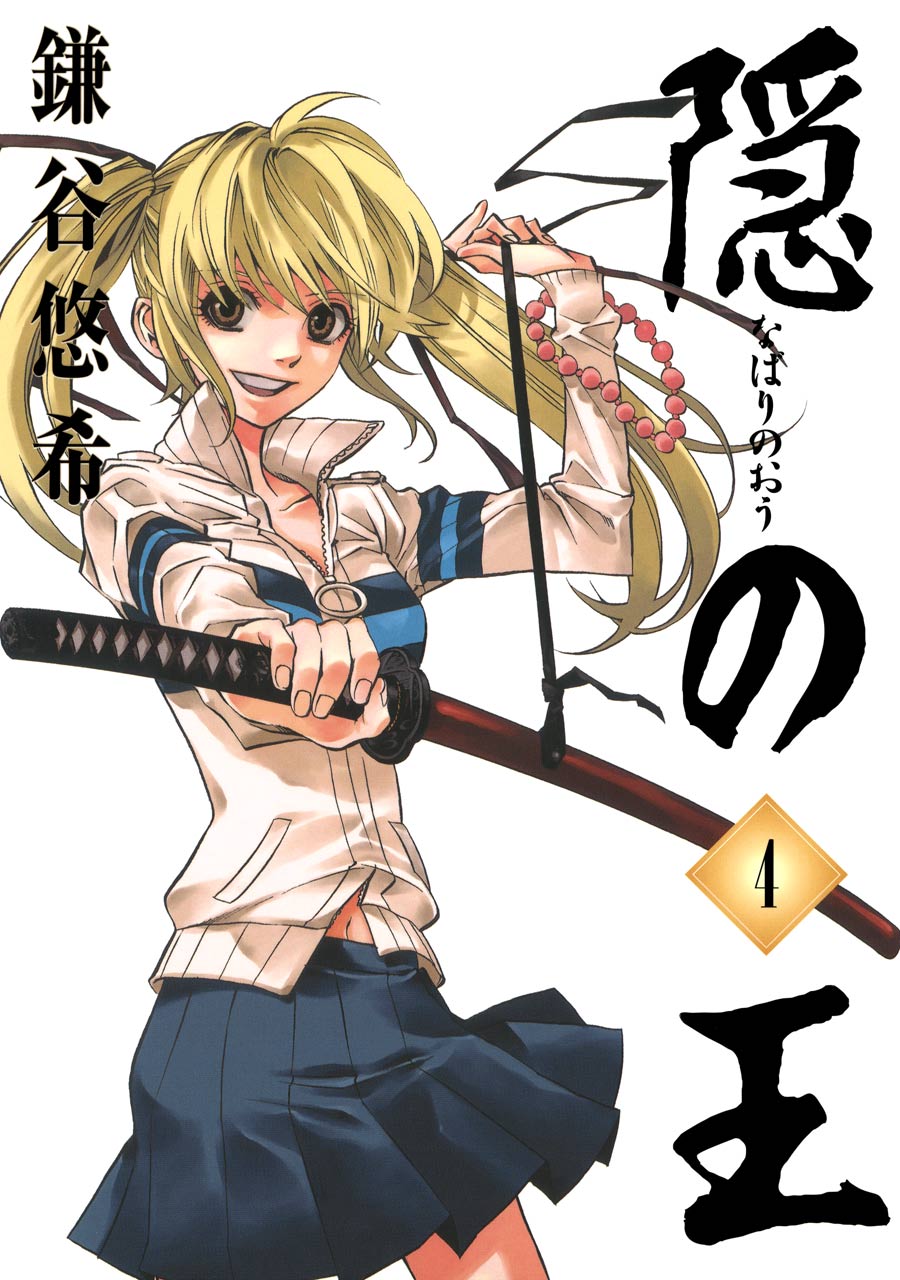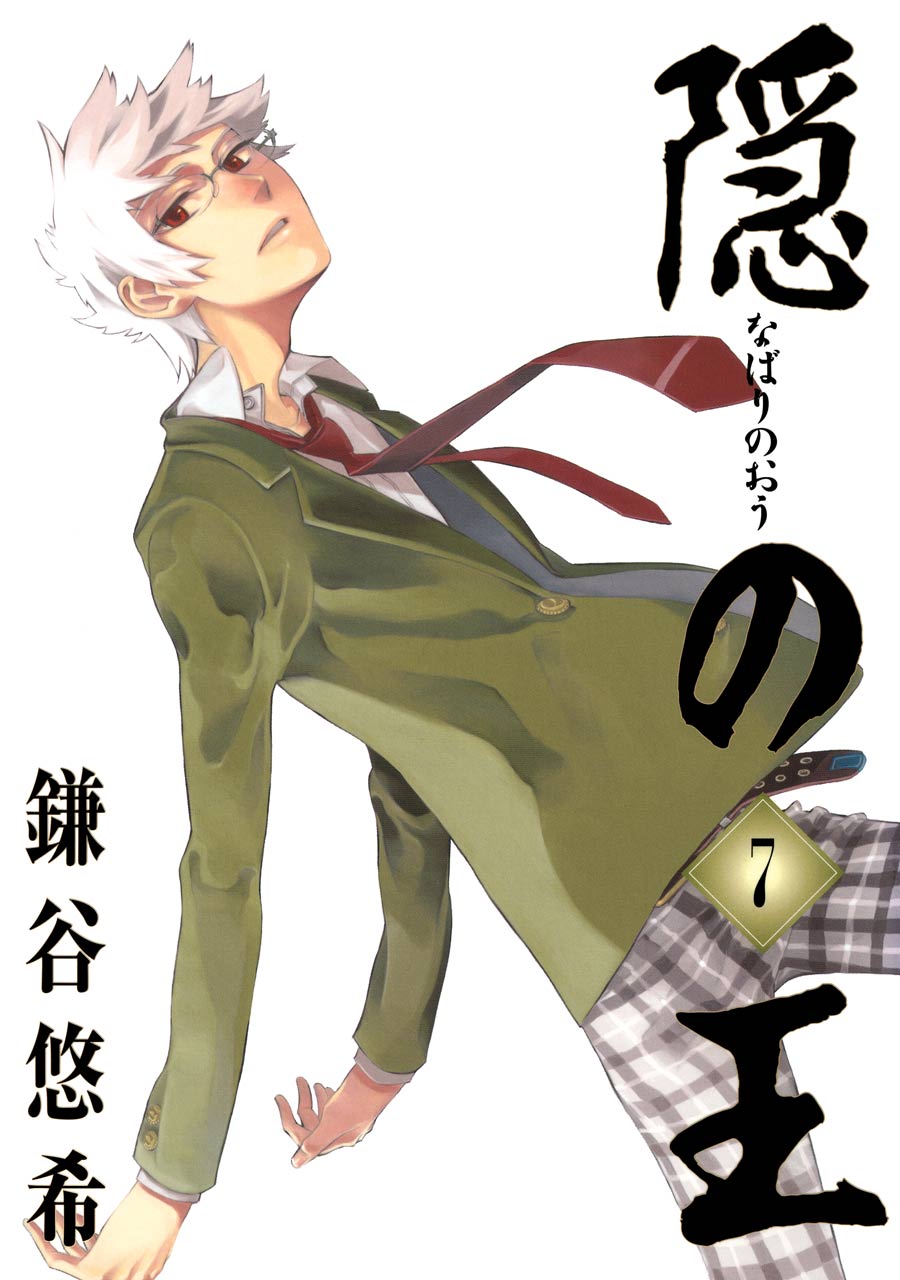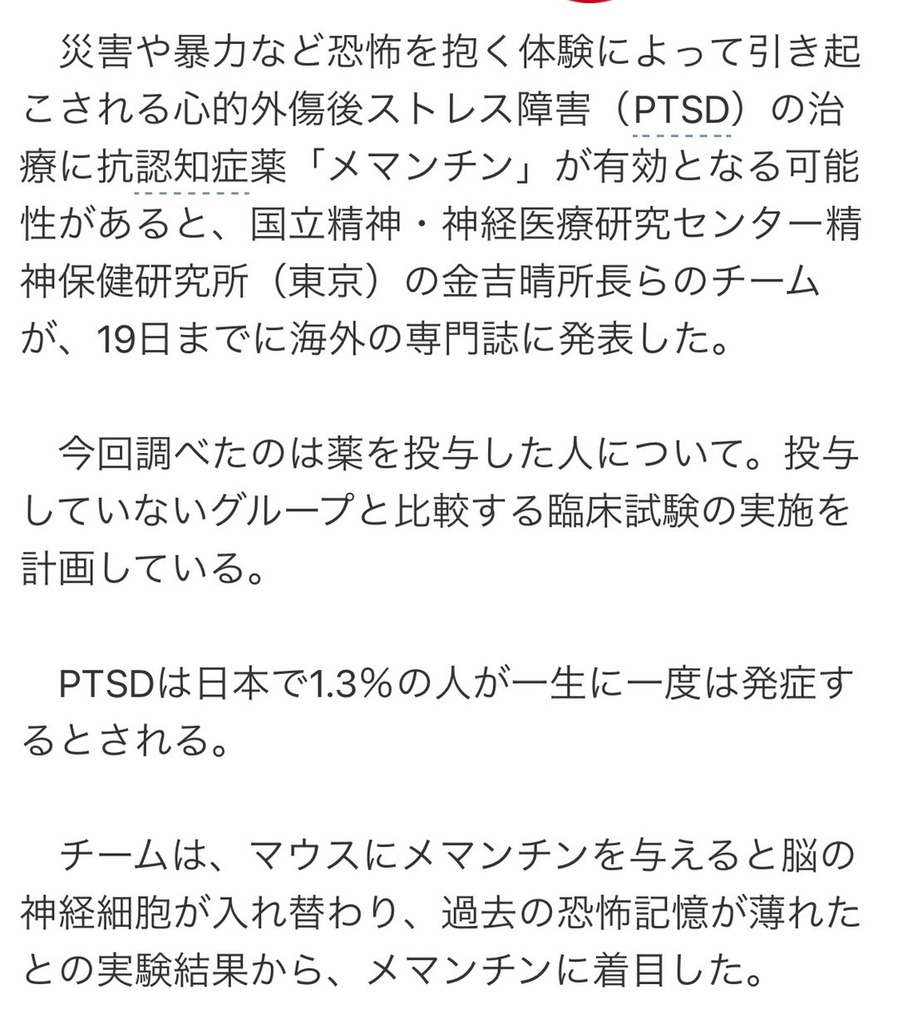ひむか の 風 に さそ われ て。 最後のKiss
牧水かるた « 若山牧水
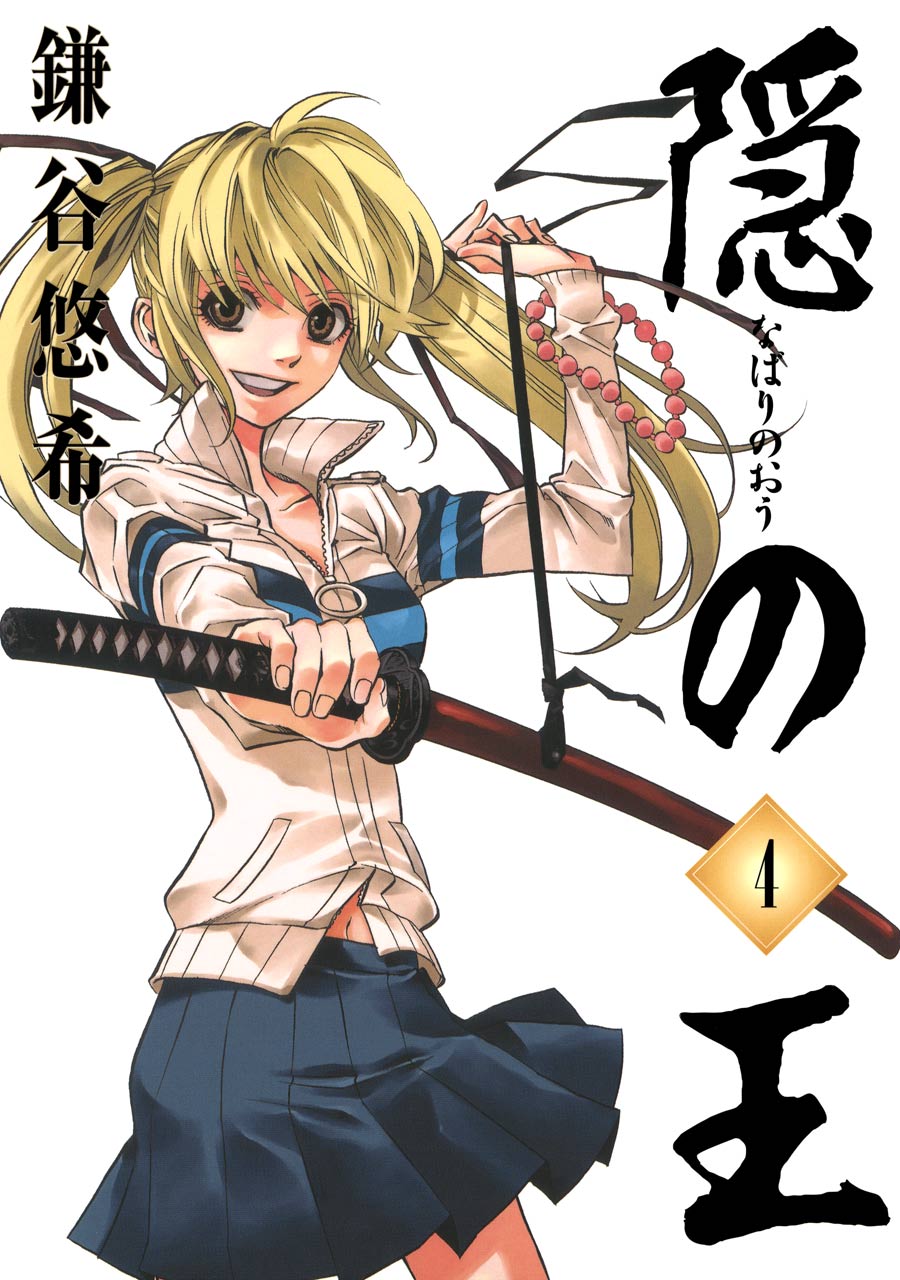
木綿 ゆう しめ身(み)に引きかけ、宝冠 ほうかん に頭 かしら を包 つつみ 、強力 ごうりき といふものに道びかれて、雲霧山気 うんむさんき の中に氷雪 ひょうせつ を踏 ふみ てのぼること八里 はちり 、さらに日月 じつげつ 行道 ぎょうどう の雲関 うんかん に入(い)るかとあやしまれ、息絶 いきたえ 身 み こごえて頂上 ちょうじょう にいたれば、日没 ぼっし て月顕 あらわ る。 宮がまだ縁先にいらっしゃったときに、この童が物陰でなにか言いたそうな素振りをしたのを見つけられて、 「どうだった」 とお聞きになるので、お返事をさし出すと、宮はごらんになって、 おなじ枝 (え) に 鳴きつつをりし ほととぎす 声は変はらぬ ものと知らずや (わたしと兄は同じ枝に鳴いていたほととぎすのようなもの 兄と声は変わらないとご存じではないのですか) とお書きになって、童に渡されるときに、 「こんなことは、けっして人に言うな。 梺 ふもと の坊 ぼう に宿 やど かり置 おき て、山上 さんじょう の堂 どう にのぼる。
16
「おくのほそ道」全文

往昔(そのむかし)この御山 おやま を二荒山 ふたらさん と書きしを、空海大師 くうかいだいし 開基 かいき の時、日光と改 あらた)めたまふ。 童が宮の返事を持って来たので、 〈素敵〉 と見たが、 〈手紙がくるたびに返事を出すのもどうか〉 と思って、お返事は出さなかった。 そういう強い句であるから、その句を先きに云って、「君が袖振る」の方を後に置いた。
7
JLPT N2 ~ばかりだ ~ばかりに
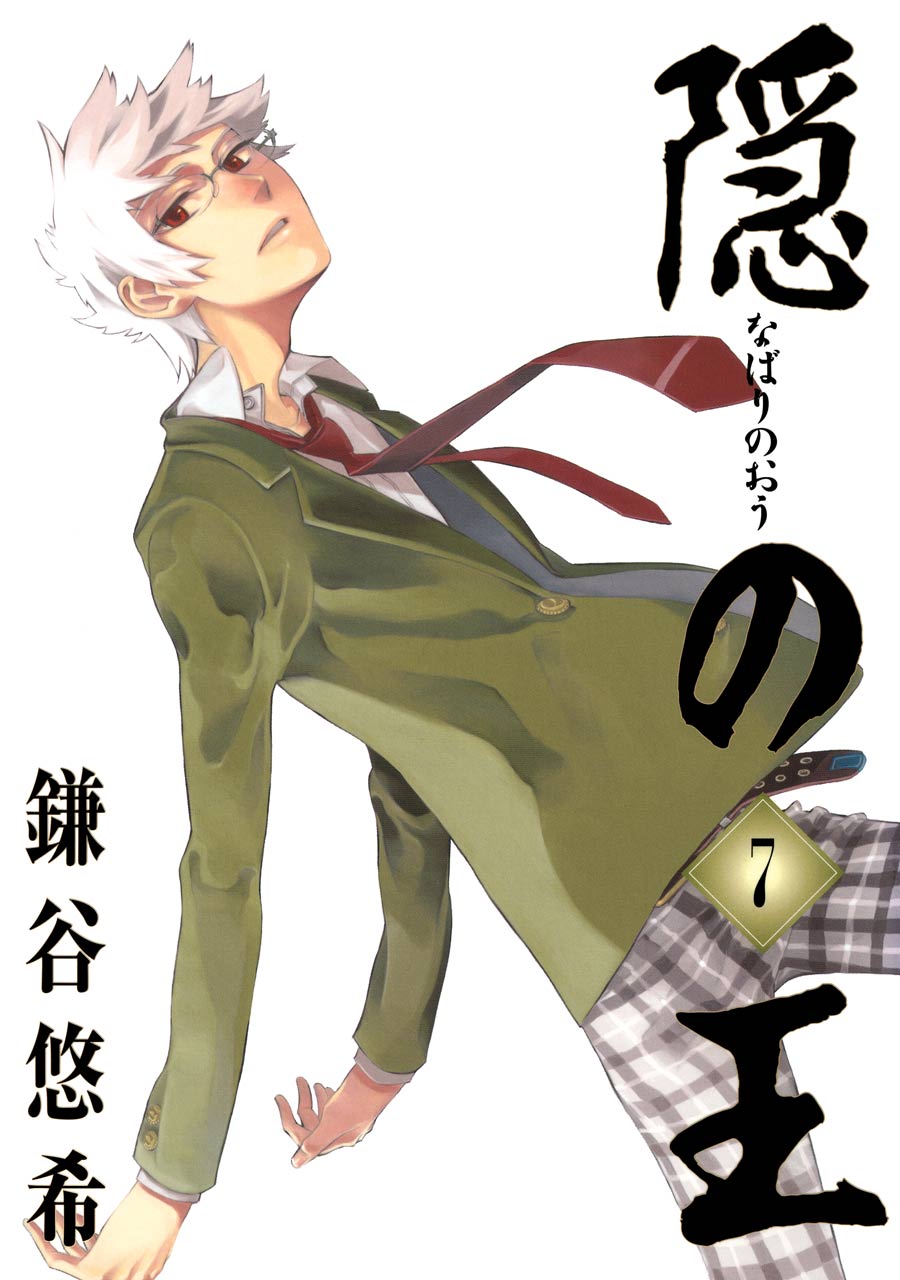
牧水かるた 歌一覧 所蔵歌集【海の聲】 白鳥はかなしからずや空の青海のあをにも染まずただよふ 母戀しかかる夕べのふるさとの櫻さくらむ山の姿よ 父母よ神にも似たるこしかたに思ひ出ありや山ざくら花 日向の國むら立つ山のひと山に住む母戀し秋晴の日や 水の音に似て啼く鳥よ山ざくら松にまじれる深山の晝を 行きつくせば浪青やかにうねりゐぬ山ざくらなど咲きそめし町 雲ふたつ合わむとしてはまた遠く分れて消えぬ春の青ぞら 地ふめど草鞋聲なし山ざくら咲きなむとする山の静けさ けふもまたこころの鐘をうち鳴らしうち鳴らしつつあくがれて行く 幾山河越えさりゆかば寂しさのはてなむ國ぞ今日も旅ゆく 檳榔樹の古樹を想へその葉蔭海見て石に似る男をも 日向の國都井の岬の青潮に入りゆく端に獨り海見る 船はてて上れる國は満天の星くづのなかに山匂ひ立つ 夕さればいつしか雲は降り來て峰に寢るなり日向高千穂 粉河寺遍路の衆のうち鳴らす鉦々きこゆ秋の樹の間に 所蔵歌集【獨り歌へる】 いざ行かむ行きてまだ見ぬ山を見むこのさびしさに君は耐ふるや あめつちにわが残し行くあしあとのひとつづつぞと歌を寂しむ 所蔵歌集【別離】 吾木香すすきかるかや秋くさのさびしききはみ君におくらむ 山ねむる山のふもとに海ねむるかなしき春の國を旅ゆく ふるさとのお秀が墓に草枯れむ海にむかへる彼の岡の上に 春白晝ここの港に寄りもせず岬を過ぎて行く船のあり 所蔵歌集【路上】 海底に眼のなき魚の棲むといふ眼の無き魚の戀しかりけり 光なきいのちのありてあめつちに生くといふことのいかに寂しき ふるさとは山のおくなる山なりきうら若き母の乳にすがりき おもひやるかのうす青き峡のおくにわれのうまれし朝のさびしさ 摘草のにほひ残れるゆびさきをあらひて居れば野に月の出づ 山々のさまりしあひに流れたる河といふものの寂しくあるかな かたはらに秋ぐさの花かたるらくほろびしものはなつかしきかな 白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけり 秋風のそら晴れぬれば千曲川白き河原に出てあそぶかな かへり來て家の背戸口わが袖の落葉松の葉をはらふゆぐれ 多摩川の砂にたんぽぽ咲くころはわれにもおもふひとのあれかし 枯草にわが寢て居ればあそばむと來て顔のぞき眼をのぞく犬 ふるさとの美々津の川のみなかみにひとりし母の病みたまふとぞ 所蔵歌集【死か芸術か】 眼をあげよもの思ふなかれ秋ぞ立ついざみづからを新しくせよ 浪、浪、浪、沖に居る浪、岸の浪、やよ待てわれも山降りて行かむ 問ふなかれいまはみづからえもわかずひとすぢにただ山の戀しき 山に入り雪のなかなる朴の樹に落葉松になにとものを言ふべき かんがへて飲みはじめたる一合の二合の酒の夏のゆふぐれ 所蔵歌集【みなかみ】 ふるさとの尾鈴の山のかなしさよ秋もかすみのたなびきて居り 母が飼ふ秋蠶の匂ひたちまよふ家の片すみに置きぬ机を いづくにか父の聲きこゆこの古き大きなる家の秋のゆふべに 納戸の隅に折から一挺の大鎌あり、汝が意志をまぐるなといふが如くに あたたかき冬の朝かなうす板のほそ長き舟に耳川くだる 海よかげれ水平線の黝みより雲よ出で來て海わたれかし われも木を伐る、ひろきふもとの雑木原春日つめたや、われも木を伐る 餘念なきさまには見ゆれ頬かむり母が芹つむきさらぎの野や 所蔵歌集【砂丘】 時をおき老樹の雫おつるごと静けき酒は朝にこそあれ 所蔵歌集【朝の歌】 わが庭の竹の林の淺けれど降る雨見れば春は來にけり やと握るその手この手のいづれみな大きからぬなき青森人よ ひつそりと馬乘り入るる津輕野の五所川原町は雪小止みせり つばくらめちちと飛び交ひ阿武隈の岸の桃の花いま盛りなり 所蔵歌集【白梅集】 夏草の茂みが上に伸びいでてゆたかになびく山百合の花 いづくより漏るるものかも部屋のうち風ありて春の眞晝なりけり 所蔵歌集【さびしき樹木】 あたりみな鏡のごとき明るさに青葉はいまし揺れそめにけり ひんがしの白みそむれば物かげに照りてわびしきみじか夜の月 中高にうねり流るる出水河最上の空は秋ぐもりせり 所蔵歌集【渓谷集】 朝山の日を負ひたれば渓の音冴えこもりつつ霧たちわたる 石越ゆる水のまろみを眺めつつこころかなしも秋の渓間に 飲む湯にも焚火のけむり匂ひたる山家の冬の夕餉なりけり 月いまだかがやかざれどわたつみにうつらふ見れば黄金ながせり よりあひて眞すぐに立てる青竹の籔のふかみに鶯の啼く ひそまりて久しく見ればとほ山のひなたの冬木風さわぐらし 所蔵歌集【くろ土】 聞きゐつつ樂しくもあるか松風のいまはゆめともうつつとも聞ゆ 日の岬うしほ岬は過ぎぬれどなほはるけしや志摩の波切りは ひんがしの朝燒雲はわが庭の黍の葉ずゑの露にうつれり うらさむここころなり來て見てぞ居る庭にくまなき秋の月夜を しみじみとけふ降る雨はきさらぎの春のはじめの雨にあらずや わがこころ澄みゆく時に詠む歌か詠みゆくほどに澄める心か みじか夜のいつしか更けて此處ひとつあけたる窓に風の寄るなり 大君の御獵の場と鎭天城越えゆけば雪は降りつつ 秩父町出はづれ來れば機織りの唄ごゑつづく古りし家並に 静かなる道をあゆむとうしろ手をくみつつおもふ父が癖なりき 香貫山いただきに來て吾子とあそび久しく居れば富士晴れにけり 所蔵歌集【山櫻の歌】 幼くて見しふる里の春の野の忘られかねて野火は見るなり 野末なる三島の町の揚花火月夜の空に散りて消ゆなり 園の花つぎつぎに秋に咲きうつるこのごろの日のしづけかりけり たち向ふ穂高が嶽に夕日さし湧きのぼる雲はいゆきかへらふ 寄る年の年ごとにねがふわがねがひ心おちゐて静かなれかし うすべにに葉はいちはやく萌えいでて咲かむとすなり山櫻花 瀬々走るやまめうぐひのうろくづの美しき頃の山ざくら花 鉄瓶のふちに枕しねむたげに徳利かたむくいざわれも寢む 相添ひて啼きのぼりたる雲雀ふたつ啼きのぼりゆく空の深みへ 寄り來りうすれて消ゆる水無月の雲たえまなし富士の山邊に 學校にもの讀める聲のなつかしさ身にしみとほる山里すぎて 所蔵歌集【黒松】 ふと見れば翼つらねてはるかなる沖邊へまへる海鳥の群 若竹の伸びゆくごとく子ども等よ眞直にのばせ身をたましひを 山川のすがた静けきふるさとに歸り來てわが勞れたるかも 若竹に百舌鳥とまり居りめづらしき夏のすがたをけふ見つるかも 故郷に墓をまもりて出でてこぬ母をしぞおもふ夢みての後に 鴉島かげりて黒き磯の岩に千鳥こそ居れ漕ぎ寄れば見ゆ 明方の月は冴えつつ霧島の山の谷間に霧たちわたる 山出でて尾長の鳥のあそぶらむ松代町の春をおもふよ 野の末にほのかに靄ぞたなびける石狩川の流れたるらむ 上つ瀬と下つ瀬に居りてをりをりに呼び交しつつ父と釣りにき 釣り暮し歸れば母に叱られき叱れる母に渡しき鮎を 潮干潟ささらぐ波の遠ければ鶴おほどかにまひ遊ぶなり 天地のこころあらはにあらはれて輝けるかも富士の高嶺は 熟麦のうれとほりたる色深し葉さえ莖さへうち染まりつつ なつかしき城山の鐘鳴り出でぬ幼かりし日ききし如くに. その跡 あと みむと雲岸寺 うんがんじ に杖 つえ をひけば、人々すすんでともにいざなひ、若 わか き人おほく、道のほど打 う)ちさはぎて、おぼえずかの梺 ふもと にいたる。
8
古今和歌集/巻十七

〔四〕 四月の三十日に、女は、 ほととぎす 世にかくれたる 忍び音を いつかは聞かむ 今日もすぎなば (五月に鳴くほととぎす 四月に鳴くのを忍び音といいますが その忍び音をいつ聞くことができるでしょう 四月も終わってしまいます 今日はぜひお越しください) と申し上げたが、宮のところには多くの人たちが参上しているときなので、童はお見せすることができない。 マサヤケミコソ(品田太吉)。
13
しゃぼん玉の結果発表|俳句ポスト365

北の方 (大納言左大将藤原済時・ふじわらのなりときの次女) も、普通の睦まじい夫婦のようではないとはいえ、宮が毎晩お出かけになれば、 〈おかしい〉 と思われるだろう。 万葉集の傑作といい秀歌と称するものも、地を洗って見れば決して魔法のごとく不可思議なものでなく、素直で当り前な作歌の常道を踏んでいるのに他ならぬという、その最も積極的な例を示すためにいきおいそういう細かしきことになったのである。 昔 むかし はこの山の上にはべりしを、往来 ゆきき の人の麦草 むぎくさ をあらして、この石を試 こころ)みはべるをにくみて、この谷 たに につき落(お)とせば、石の面 おもて 下ざまにふしたりといふ。
6
日向のさざれ石
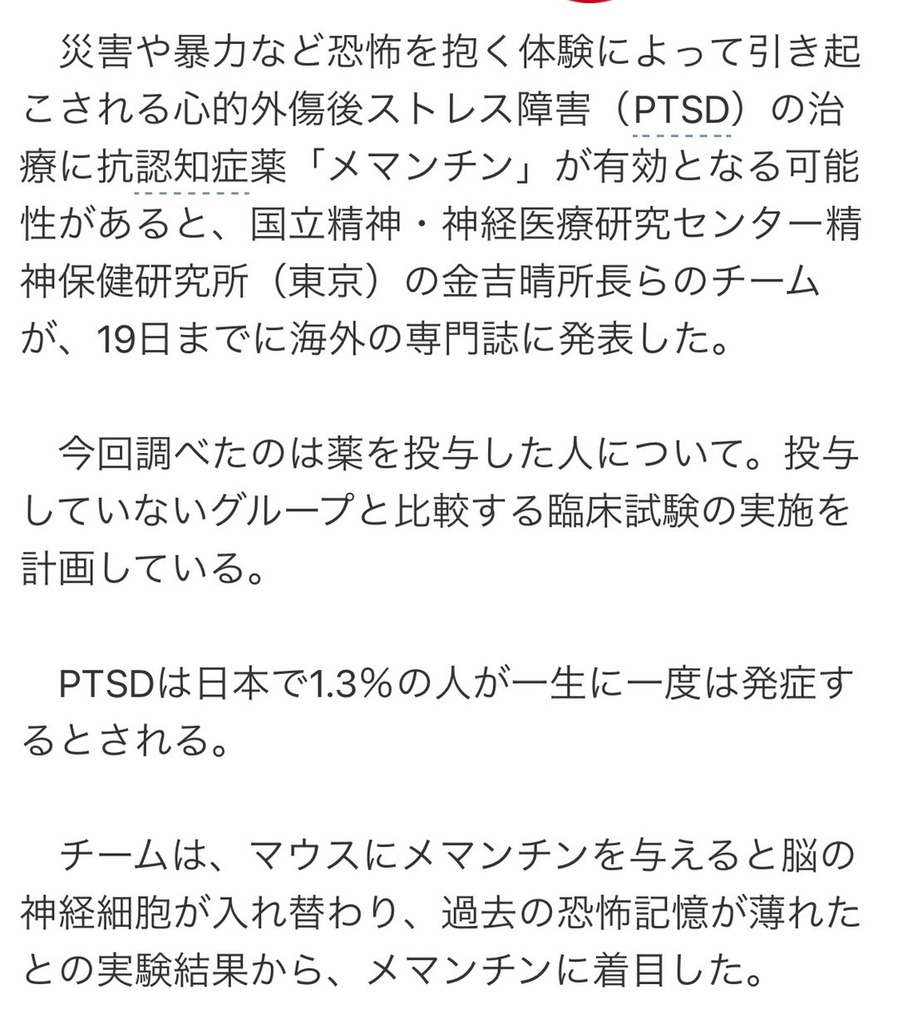
しばらくは 瀧 たき に籠 こも るや 夏 げ の初 はじめ (なす) 那須 なす の黒ばねといふ所 ところ に知人 しるひと あれば、これより野越 のごえ にかかりて、直道 すぐみち をゆかんとす。 中にも、二人の嫁 よめ がしるし、まず哀 あわ)れなり。
3
最後のKiss

浜(はま)はわづかなる海士 あま の小家 こいえ にて、侘 わび しき法花寺 ほっけでら あり。 サヤケシトコソ(春満)。 お話だけでも〉 と思って、西の妻戸に円座 (藁、菅などで渦巻状に編んだ敷物) をさし出してお入れしたのだが、世間の人がそう言うせいか、普通の容姿ではなく優雅で美しい。
4