放射線取扱主任者 難易度

過去問で誤った問題の解説を見ても言葉や公式が少しも理解できないといった場合は、その基本から勉強しなおしましょう。 あきらめず、コツコツと勉強を続けてください。 しかし、法令の演習問題は試験で問われがちな 微妙な言葉の違いを覚える上でとても役に立つので何度か繰り返し解いてみると良いと思います! 概論が難しすぎて読み進められない!という方はより簡単にまとめられた以下の参考書を使っても良いと思います。
16
過去問で誤った問題の解説を見ても言葉や公式が少しも理解できないといった場合は、その基本から勉強しなおしましょう。 あきらめず、コツコツと勉強を続けてください。 しかし、法令の演習問題は試験で問われがちな 微妙な言葉の違いを覚える上でとても役に立つので何度か繰り返し解いてみると良いと思います! 概論が難しすぎて読み進められない!という方はより簡単にまとめられた以下の参考書を使っても良いと思います。
16
放射線障害防止法の放射線とは、電磁波または粒子線のうち、直接または間接的に空気を電離する能力をもつもので• 第1種放射線取扱主任者試験• 試験内容 第1種・第2種の試験は、公益財団法人原子力安全技術センターが実施するもので、全科目択一問題のマークシート方式です。
2
なんだかんだ大学入学後に一番勉強した試験は作業主任者だと思います。 同時に第1種及び第2種の試験を受けることも可能である。 また、第三種放射線取扱主任者は、試験がなく資格講習のみです。
12
原子核の基本・・・クーロン力、エレクトロンボルト、質量欠損、プランク定数等の計算は基本なので確実に• 放射線の基本的な安全管理に関する課目• 第3種放射線取扱主任者は、講習を受講すればそのまま取得できます。 この問題では粒子線の種類に加えて、速度が与えられる場合とエネルギーが与えられる場合があります。 不安な気持ちや焦る気持ちもあるかとは思いますが、できるだけ平常心を保ち、今までの復習に時間を費やして下さい。
1
放射線の基本的な安全管理に関する課目• どちらかと言えば、会社で信頼されている中堅社員が、ステップアップのために取得する資格です。 上記3科目に関しては来年度も変更がなさそうですが、法令改正の影響で法令と新しい3科目はかなり予想が難しいところですね。 試験問題の大半は、講義や実習の際に出てくる問題のようです。
14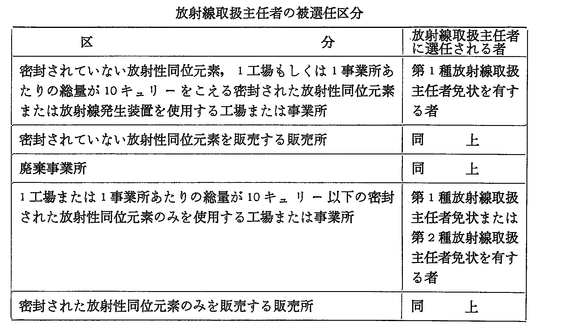
通商産業研究社等から参考図書も出版されていますので、素養があれば独学でも問題ないでしょう。 毎年同じことを書いていますが、試験に臨むにあたっての心構えです。 この第二種放射線取扱主任者は、原子力発電所、関連会社、研究所、工場などで計器の校正などに使用される、密閉された放射線同位元素を取り扱うための資格です。
7