門出・土佐日記 現代語訳・品詞分解・読み方

年ごろあそびなれつるところを、あらはにこぼち散らして、たちさわぎて、日の入りぎはの、いとすごく霧りわたりたるに、車に乗るとて、うち見やりたれば、人まにはまゐりつつ、額をつきし薬師仏の立ち給へるを、見捨てたてまつる悲しくて、人知れずうち泣かれぬ。 「かご」は帯の留め金で「かごと」と掛ける。

年ごろあそびなれつるところを、あらはにこぼち散らして、たちさわぎて、日の入りぎはの、いとすごく霧りわたりたるに、車に乗るとて、うち見やりたれば、人まにはまゐりつつ、額をつきし薬師仏の立ち給へるを、見捨てたてまつる悲しくて、人知れずうち泣かれぬ。 「かご」は帯の留め金で「かごと」と掛ける。

2月9日 続 『』 : 渚の院を見て、在原業平の歌を思い出す。
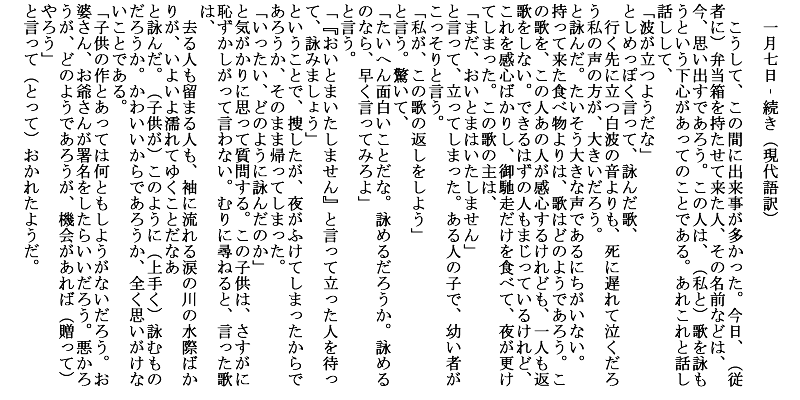
夫差曰、「吾無以見子胥。

「黒=原文」・「 青=現代語訳」 作者: 菅原孝標女 すがわらのたかすえのむすめ 解説・品詞分解はこちら 東路の道の果てよりも、なほ奥つ方に生ひ出でたる人、 東海道の終わり(の所)よりも、さらに奥の方で生まれ育った人(=作者自身のこと)は、 いかばかりかはあやしかりけむを、いかに思ひ始めけることにか、 どんなにか見すぼらしかっただろうに、どうして思い始めたことであろうか、 世の中に物語といふもののあなるを、 「世の中に物語というものがあるそうだが、 いかで見ばやと思ひつつ、つれづれなる昼間、 宵 よひ 居 ゐ などに、 どうにかして見たいとしきりに思い続けて、何もすることがなく退屈な昼間や、夜起きているときなどに、 姉・ 継母 ままはは などやうの人々の、その物語、かの物語、光源氏のあるやうなど、ところどころ語るを聞くに、 姉や継母などというような人々が、あの物語、この物語、(源氏物語の)光源氏の有様など、ところどころ語るのを聞くと、 いとどゆかしさまされど、 ますます読みたい気持ちが強くなるけれども、 わが思ふままに、そらにいかでかおぼえ語らむ。 。
13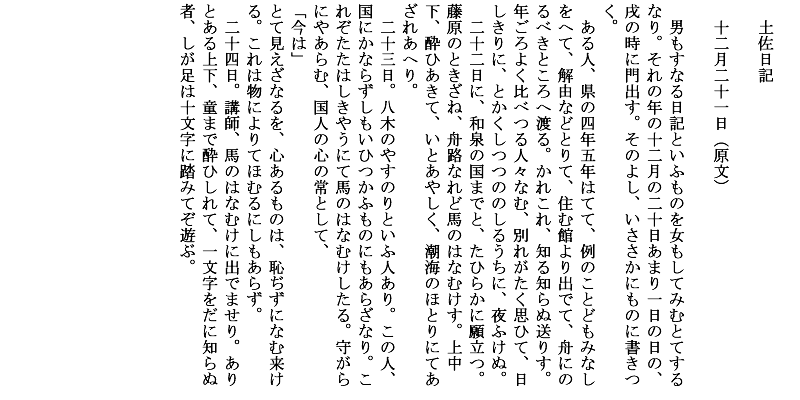
承平4年(934)年12月21日に、国守として赴任した土佐を出発し、翌年2月16日に、京の自宅に帰るまでの出来事を、和歌を交えながら記した。 夫差其の尸を取り、盛るに鴟夷を以てし、之を江に投ず。 某年の12月21日の午後八時ごろ、旅立つ。
16
解由(げゆ)など取りて、住む館より出でて、船に乗るべき所へ渡る。 (後任者から)解由状などを受け取って、住んでいる官舎を出て、舟に乗ることになっている所に移る。 太宰嚭子胥謀の用ゐられざるを恥ぢて怨望すと譖す。
7