国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト 公益法人information
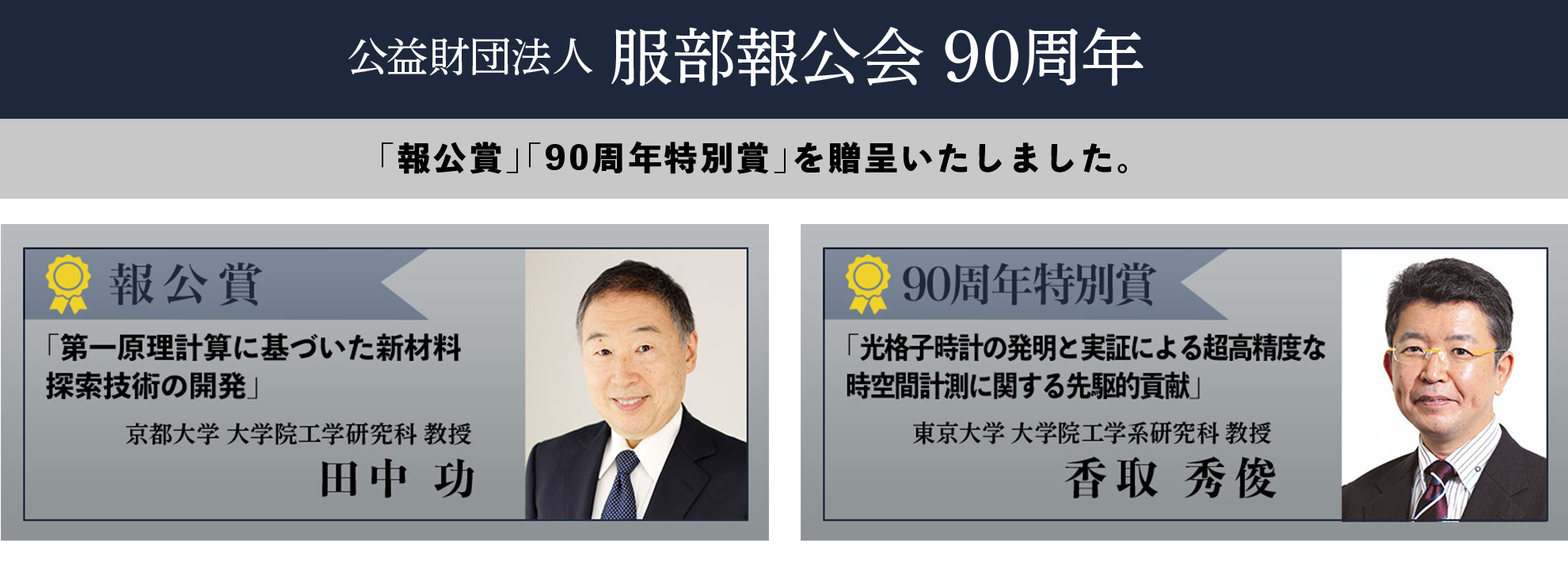
(同法162条)。
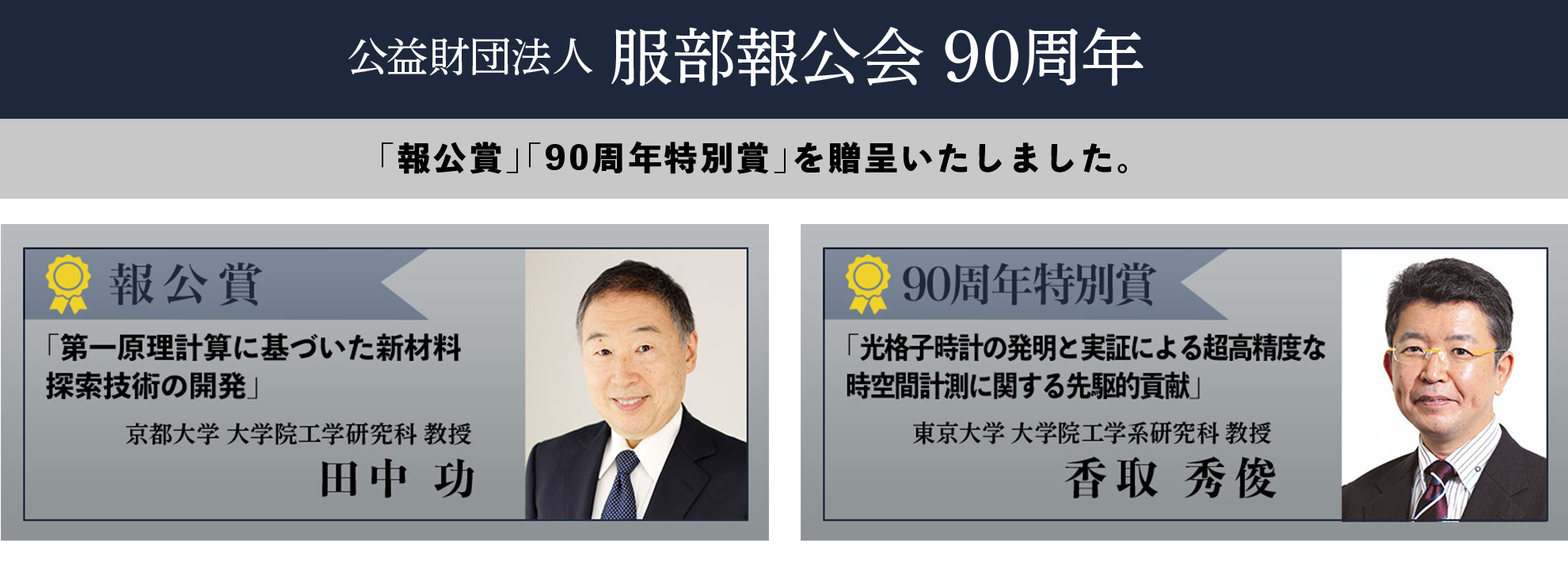
(同法162条)。

すなわち、遺贈義務者(遺贈の履行を行う義務がある相続人など)は、受遺者(遺贈を受ける者)となる設立者に対して、遺贈の承認または放棄をすべき旨の催告をします(民法987条)。 では、一般社団法人と株式会社の違いはどこにあるのでしょうか。
16遺言で財産の拠出が行われた場合、財産は、遺言が効力を生じた時から一般財団法人に帰属したものとみなされます。 事業目的に制限がない。
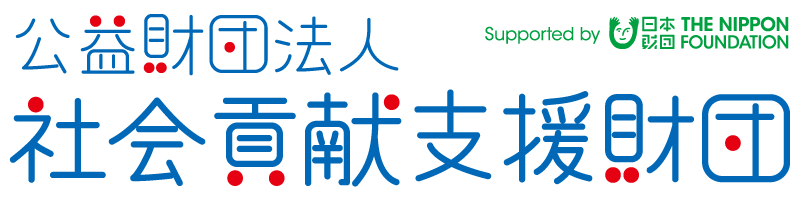
認定法 2,3条• 改正前の民法では法人を公益法人(改正前民法34条)と営利法人(改正前民法35条)に分け、営利法人については主に商法(のちに会社法)で規律され許可を要することなく設立できるとされていたのに対し、公益法人については民法で設立に主務官庁の許可が必要とされていた。 資金調達および設備投資の見込みを記載した書類とは、当期中における借入れの予定があるかどうかを記載します。

定款は、株式会社では「会社の憲法」に例えられ、作成を義務付けられた重要書類の1つです。 一般財団法人の活動は、すべて定款に記載した内容に従って行われなければなりません。
7
8-1 申請書類を作成する 公益認定申請先の行政庁は、公益社団法人と同様で、法人の種類で異なります。
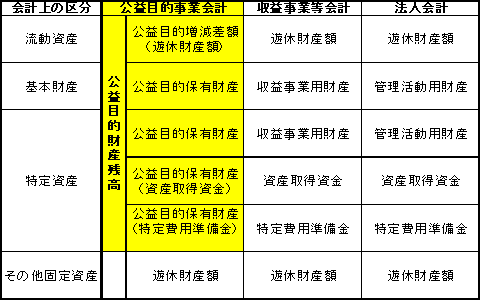
生前処分により財産の拠出を行う場合は、民法の規定が準用されます。 脚注 [ ] []• 8-2 行政庁の定款審査を受ける 一般財団法人が公益財団法人に移行するとき、その定款の変更の案の内容が公益法人の規定に適合するものであるかどうかを調べる定款審査を受けることになります。 営利法人である等と異なり、設立者にまたはを受ける権利を与えるは無効となる(一般社団・財団法人法153条3項2号)。