「ローマ法王」「ローマ教皇」という二つの呼称について

それ以前の非イタリア人の教皇の先例は、ともともいえるの、非ヨーロッパ出身の先例は出身のまで遡る。
8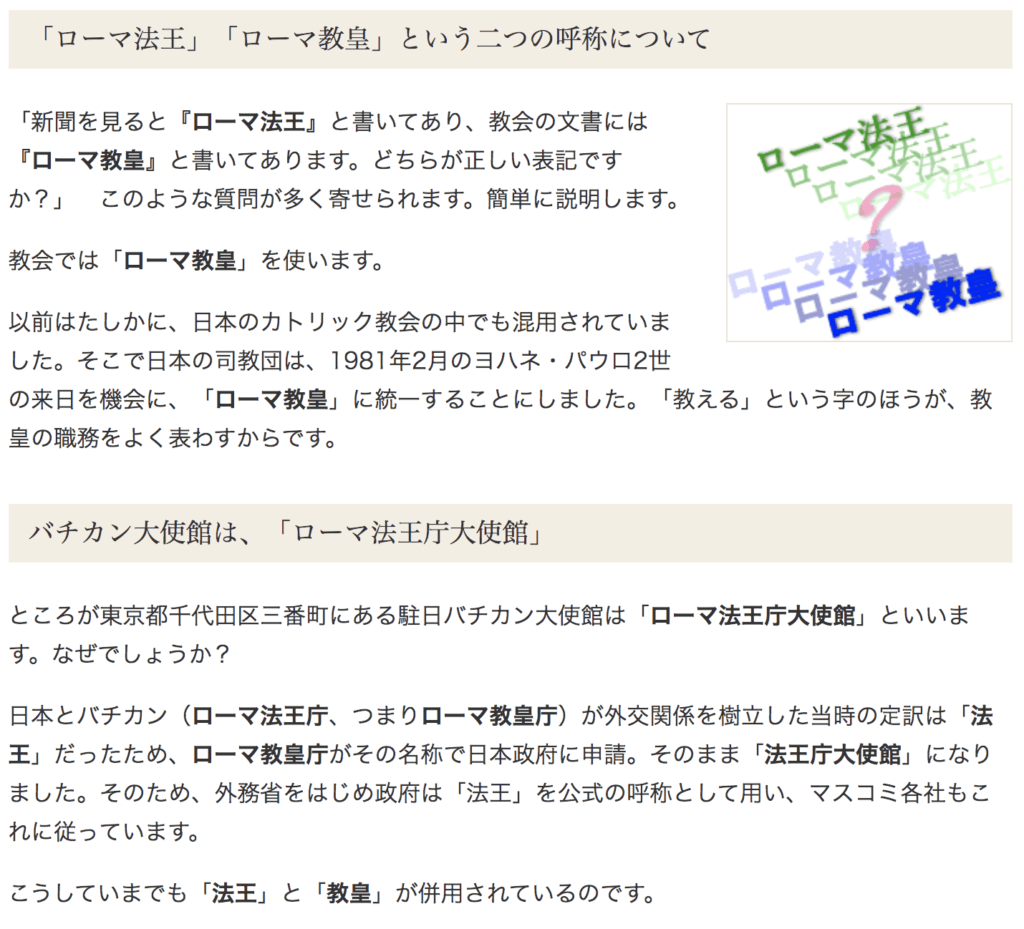
語源は「パパ」つまり「父」と同じです。 気になる説明ですが、次のように書いてありました。 教皇領の成立の根拠とされた「」が偽書であることは以降広く知られていたが、教皇領そのものは統一まで存続した。
2
これにより、現在に至るまで、 イタリアにおけるカトリック教会の特別な地位を保証するものとなりました。 キリスト教全体が20億人で、その中でのカトリック13億人ですから、最大宗派として有名であることにも納得がいきますね。 「『教える』という字のほうが、教皇の職務をよく表わすから」 というのがその理由だ。
12
どちらにせよ、天皇陛下は世界中の国から敬意を示されている存在ということで、とても世界的地位ランキングTOPということがわかりました。 日本政府による呼称 [ ] 官報や外務省の文書では、戦前から長らく基本的には「法王」の語が用いられていたが、教皇が使用されないわけではなかった。 。

家族内での父親のイメージに近い権威的・指導者的な役割を担う人という意味です。 しかもこの「法王」としたのは外務省が勝手に決めたわけではなく、相手国が申請するとき「ローマ法王庁」で申請してきたからだとされているのです。
10
放送では一般に慣れ親しんだ『ローマ法王』を使う つまり、ここまで3種類の辞書で比較をしましたが、意味は両者とも同じということがわかりました。
3
「法王」と「教皇」正しいのはどっち? これまで日本のカトリック中央協議会が「教皇」での呼称統一を呼びかけてきて、今回日本政府が「教皇」を正式な呼称とすると決めたことで、日本での正式名称は「教皇」となることになりました。
14
「コンクラーべ」の名前の由来どおり議場には鍵がかけられてしまうからです。 とはいえ、これまでずっと「法王」を使ってきたメディアの対応が統一され浸透するにはちょっと時間がかかるかもしれませんね。 ペトロは全教会の師であるが、教皇はローマの()に過ぎない。