「是非」の意味と使い方を例文付きで紹介!類語「可否」との違い、英語表現も
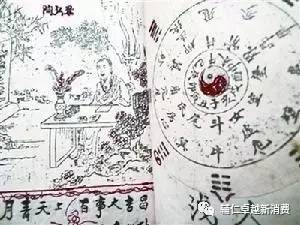
心よりお待ち申し上げております。 鎌倉時代や戦国時代に書かれた書物にも確認できるとされています。 ・ 是非を問う ・ 是非もなし ・ 是非に及ばず ・ 是非も知らず これらの「是非」は名詞として使用されています。
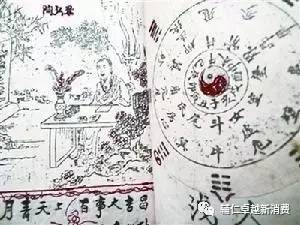
心よりお待ち申し上げております。 鎌倉時代や戦国時代に書かれた書物にも確認できるとされています。 ・ 是非を問う ・ 是非もなし ・ 是非に及ばず ・ 是非も知らず これらの「是非」は名詞として使用されています。

しかしながら状況によってはフォーマルな要素を弱めることで、さらに強い意志を示すことができるシチュエーションもありますので、敢えて「何としてでも」というようなカジュアルな要素が強い言い回しを使うのも一考です。 特に、目上の人などに使う場合は「是非もないです」と使うと丁寧かつ状況が伝わりやすくなります。
5
言い方は、程よく丁寧に伝えるよう心掛けましょう。 しかしながら「良いか悪いか」というのはあくまでも主観になるので結論ではありません。 例文ではイベントへの参加を強く促しています。
13
ほかの言葉に置き換えることもできるのですが、「是非」という言葉を使うことで非常にフォーマルな言い回しになります。 それよりも丁寧でへりくだった表現がしたいという時には、「是非」ではなく「何卒」や「どうか」を使用すると、そのような印象になります。 例文を見ていきましょう。
17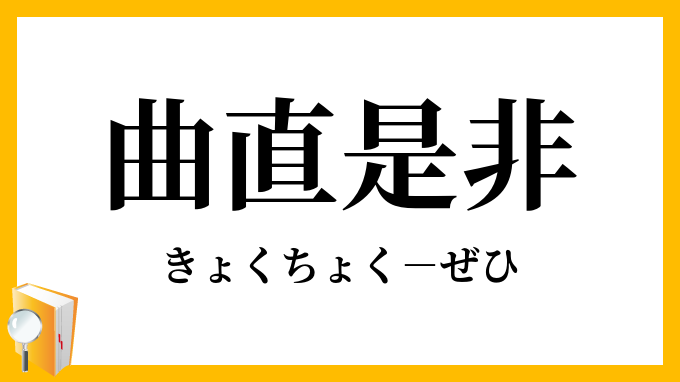
元々は「神が承諾しない」を表す漢字です。 (是非ともその研修会には出席させてもらいます) 是非(ぜひ)の英語は強調表現はその都度翻訳し返答には熟語を使う 是非(ぜひ)の英語は強調表現はその都度翻訳し、返答には熟語を使うことが挙げられます。 しかし、この「是非もなし」には「どうしようもない」という諦めの意味だったと考えられる他、「あれこれ話し合っている場合ではない、戦うしかない」という前向きな決断であったとも言われています。
15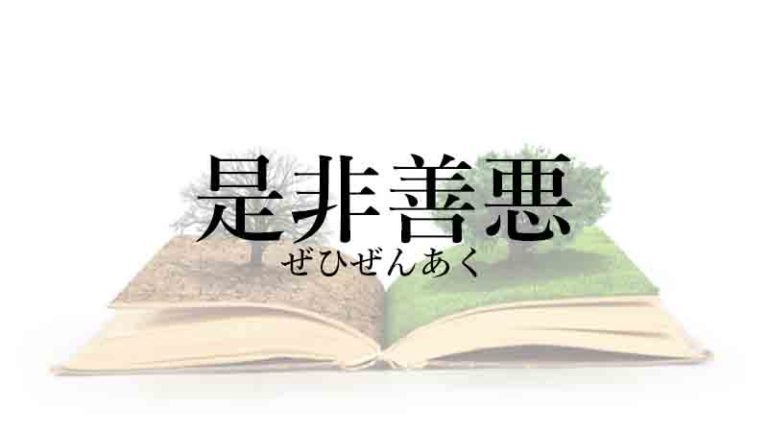
」 締め切りが取引先内で決まっていることなので、 本当は不服だが 「仕方ない」というニュアンスに受け取られかねません。 certainly 絶対に• 元々は「祈りを神が許す」といった意味を表す漢字です。
10
「しょうがない、あきらめよう」と「戦うしかない」のどちらの意味にも取れるため、どちらの解釈をするか議論が繰り広げられています。 「是非」という言葉を使うと非常に強い意志を表すことができるものの、フォーマルさが含まれることは否定できません。 目上の人に対しても使える表現ですが、連続して使うと失礼な印象を与える可能性があります。
16