『郵便的不安たち』について ――東浩紀と柄谷行人(第二回)

しかし、少し調べてみるとこの著作はかなり売れていて、実際に台湾や韓国だけでなく、日本でも柄谷氏を「世界史の構造」の人、と認識している世代が出始めているというようなことを知った。 そうなるとおそらくは暴力革命も必要ではなくなり、日本で支持を失った大きな部分を修正できるという考えも、これは明記はされていないがあったのではないかと私は想像した。 その中心にすえられたのが、を中心とした『』の読み直し・再解釈である。
12
しかし、少し調べてみるとこの著作はかなり売れていて、実際に台湾や韓国だけでなく、日本でも柄谷氏を「世界史の構造」の人、と認識している世代が出始めているというようなことを知った。 そうなるとおそらくは暴力革命も必要ではなくなり、日本で支持を失った大きな部分を修正できるという考えも、これは明記はされていないがあったのではないかと私は想像した。 その中心にすえられたのが、を中心とした『』の読み直し・再解釈である。
12
2004年5月には近畿大学人文研での講義をもとにした『近代文学の終わり』 を に発表。 なお大塚は、柄谷のNAM解散断行を肯定している。 その理論的仕事は編集長下の『』(1973 - )()に発表されることが多く 、とともに1983年の『』で始まる「ブーム」「」の一端を70年代において準備した。
4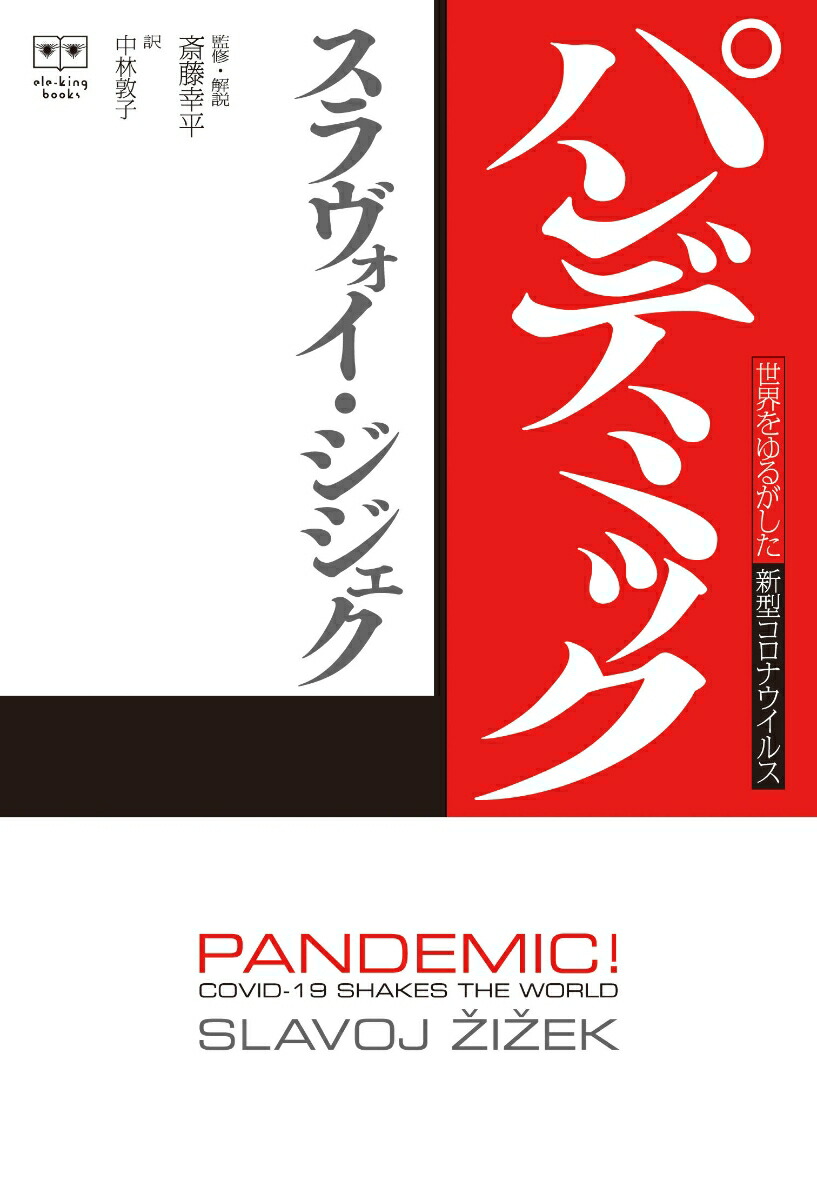
野球をプレイするのも好きで、80年代、、中上健次らと「カレキナダ」という草野球チームを作っていたことがある。
5
だったらバイデン、ハリスのお手並み拝見である。 20代の柄谷は、を高く評価していたことが初期論文の「思想はいかに可能か」や「心理を越えたものの影」からうかがわれる。 だからときどき棚卸しをして、各階に配架して隙間をあける。
20
印税まで支払ったのに発行を遅らさざるをえない出版社もあり、日本の小説を陳列しないという貼り紙を出した書店もありました。 その度に内容を大きく入れ替えているため、私たちは『郵便的不安たち』のテクストを二種類に分けることができるように思われる。
13
著名な活動家など多数が参加し、最大700人の会員数を数えた。 けれども、AWSのギガバイトあたりの転送料金を調べたり、放送可能時間の計算式を組み立てたりしながら、ぼくがずっと考えていたのはそんなことだった。 1987年5月の第30回から同賞の選考委員に就任。
16
だが「この私」には、この座談会とシンポジウムにおける柄谷は「嫌み」を言っているというより、もっと深刻な人間観・世界観の食い違いから東とのを引き起こしてしまっているように感じられる。 いつも300冊くらいが少しずつ着替えているくらいだと思う。 2006年3月に近畿大学の運営に不満を持ち近畿大学国際人文科学研究所 所長を、副所長で、研究者の(柄谷とともに新坂口安吾全集を編集)とともに辞任。
4
交流のあった文化人の話を聞くのも楽しみでした。

同書の整理によれば、人間がものを交換する様式には、歴史的に「互酬」「略取と再分配」「商品交換」の3つのタイプがある。 「なんか俺はもっとこう、本質的な会話をしたいと思って。
10