「解決済み」の徴用工問題で誤解が多い理由 WEDGE Infinity(ウェッジ)

韓国大法院判決はこの日本の確定判決を覆した。
5
この「不合意の合意(agree to disagree)」は政治リーダーによる賢慮であると評価されてきた。 人権や人道という問題に非常に敏感で、司法が最後のとりでのような面がある。
7
それによって徴用工個人は未だ賠償金を貰えておらず、個人ベースで日本に直接訴訟を起こしている、という構図です。 元徴用工を巡っては、日本でも元徴用工による訴訟が行われたが、原告敗訴の判決が確定している。
20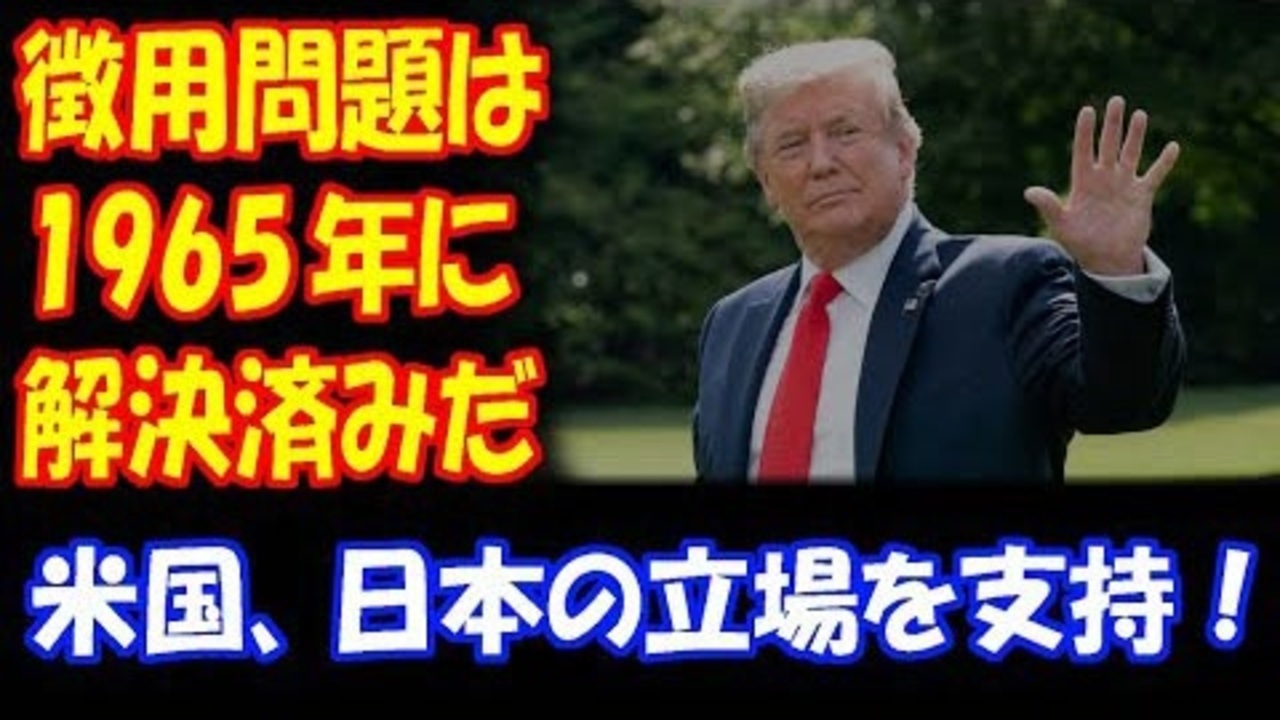
元慰安婦への損害賠償を巡る訴訟で、ソウル中央地裁が日本政府に元慰安婦らへ1人当たり1億ウォン(約950万円)の賠償を命じた判決が1月23日、確定した。 しかし、およそ2カ月後に、1910年8月29日に締結された「韓国併合条約は、当時の国際関係等の歴史的事情の中で法的に有効に締結され、実施された」と国会で答弁すると、植民地支配の合法性に関する限り、左派も含めた日本の「歴史認識の限界」と受けとめられた。
17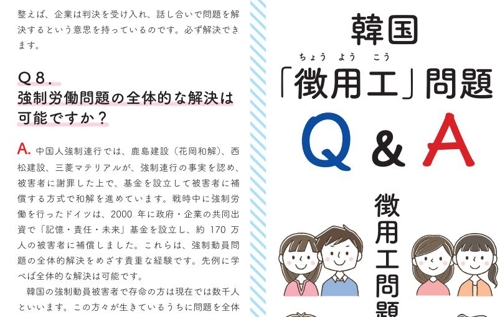
元徴用工や元慰安婦の訴訟の判決から言えることは、20世紀までは抑制的だった韓国司法も、そうではなくなってきた、ということだ。 徴用工裁判での韓国・大法院の判決に、「解決済みの問題を蒸し返した」「ちゃぶ台返し」「国際法上ありえない判断」など日本の政府関係者やメディアは一様に猛反発した。