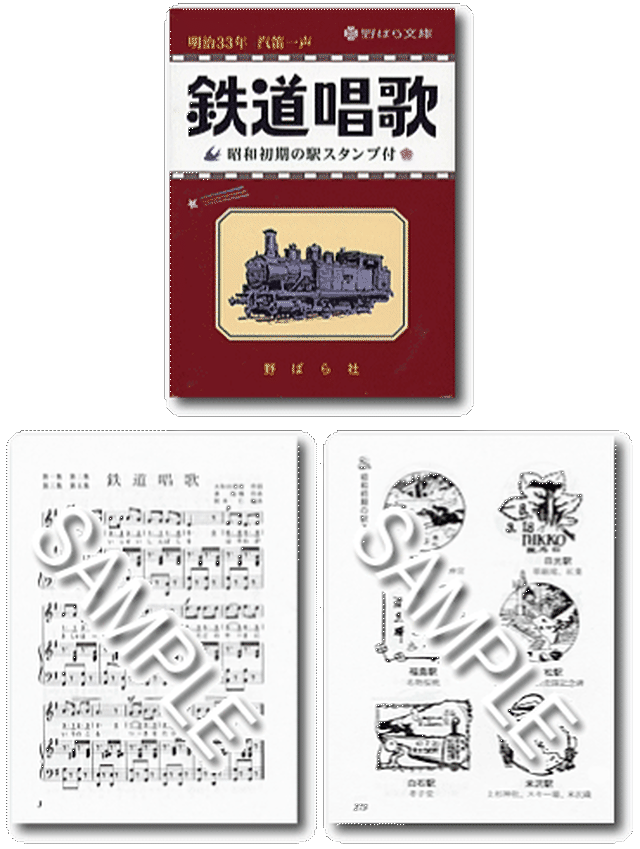鉄道 唱歌。 鉄道唱歌とは
鉄道唱歌

底本:• 鞘 ( さや )より 拔 ( ぬ )けておのづから 草 ( くさ )なぎはらひし 御 ( み ) 劒 ( つるぎ )の 御 ( み ) 威 ( いつ )は 千代 ( ちよ )に 燃 ( も )ゆる 火 ( ひ )の 燒 ( やい ) 津 ( づ )の 原 ( はら )はこゝなれや• 峰 ( みね )にのぼれば 地圖 ( ちづ ) 一 ( ひと )つ ひろげし 如 ( ごと )く 見 ( み )えわたる 常 ( ひた ) 陸 ( ち )の 國 ( くに )のこゝかしこ 利根 ( とね )のながれの 末 ( すえ )までも• 日 ( につ ) 光 ( くわう ) 見 ( み )ずは 結構 ( けつかう )と いふなといひし 諺 ( ことわざ )も おもひしらるゝ 宮 ( みや )の 樣 ( さま ) 花 ( はな )か 紅葉 ( もみぢ )か 金襴 ( きんらん )か• 宰 ( さい ) 府 ( ふ )わかれて 鳥栖 ( とす )の 驛 ( えき ) 長崎 ( ながさき )ゆきのわかれ 道 ( みち ) 久留米 ( くるめ )は 有 ( あり ) 馬 ( ま )の 舊 ( きう ) 城 ( じやう ) 下 ( か ) 水天宮 ( すゐてんぐう )もほどちかし• 桔梗ヶ丘の古戦場 満目荒涼風寒く 北信満峰巍々として 深志の城は目に近し• 交通網の充実をみた1928年(昭和3)、鉄道省は東京日日新聞と大阪毎日新聞の共催で『新鉄道唱歌』を懸賞募集したことがある。 海 ( うみ )にいでたる 廻 ( くわい ) 廊 ( らう )の 板 ( いた )を 浮 ( うか )べてさす 汐 ( しほ )に うつる 燈 ( とう ) 籠 ( ろ )の 火 ( ひ )の 影 ( かげ )は 星 ( ほし )か 螢 ( ほたる )か 漁 ( いさり ) 火 ( び )か• 汽笛一声我が汽車は はや離れたり飯田町 牛込市ヶ谷堀の端 四ツ谷出づれば信濃町• 關本 ( せきもと )おりで 〔 〕 平潟 ( ひらかた )の 港 ( みなと )にやどる 人 ( ひと )もあり 岩 ( いは )の 中道 ( なかみち )ふみわけて 磯 ( いそ )うつ 波 ( なみ )も 聞 ( き )きがてら• 神奈 ( かな ) 川 ( がは ) 過󠄁 ( す )ぎて 平󠄁沼 ( ひらぬま )の あなたを 見 ( み )れば 百船󠄂 ( もゝふね )の 煙󠄁 ( けむり )は 空󠄁 ( そら )をこがすまで こゝ 橫濱 ( よこはま )の 大 ( おほ ) 港󠄁 ( みなと )• 沼 ( ぬま ) 津 ( づ )の 海 ( うみ )に 聞 ( きこ )えたる 里 ( さと )は 牛臥 ( うしぶせ ) 我 ( が ) 入道󠄁 ( にふだう ) 春 ( はる )は 花󠄁 ( はな )さく 桃 ( もゝ )のころ 夏 ( なつ )はすゞしき 海 ( うみ )のそば• 山 ( やま )はうしろに 立 ( た )ち 去 ( さ )りて 前󠄁 ( まへ )に 來 ( きた )るは 琵琶 ( びは )の 海 ( うみ ) ほとりに 沿󠄀 ( そ )へる 米原 ( まいばら )は 北陸線 ( ほくりくせん )の 分󠄁 ( ぶん ) 岐 ( き ) 點 ( てん )• ここでは「 単語 ( ルビ )」の形で再現しています。
鉄道唱歌/奥州・磐城篇

大陸横断鉄道の工事現場で働く工夫達の様子が描かれている。
「鉄道唱歌」世界の童謡・唱歌無料ダウンロード

中央線鉄道唱歌 [ ]• 雪 ( ゆき )のあした 月 ( つき )の 夜半 ( よは ) あそぶ 人 ( ひと )はいかならん みれど/\ 果 ( はて )もなき 二 ( ふた ) 子 ( ご ) 島 ( じま )の 夕 ( ゆふ )げしき• いよ 〳 〵 近󠄁 ( ちか )く 馴 ( な )れくるは 近󠄁 ( あふ ) 江 ( み )の 海 ( うみ )の 波 ( なみ )のいろ その 八景 ( はつけい )も 居 ( ゐ )ながらに 見 ( み )てゆく 旅󠄁 ( たび )の 樂 ( たの )しさよ• 作曲:春江堂書籍より• 三 ( み ) 島 ( しま ) 驛 ( えき )には 官 ( くわん ) 幣󠄁 ( ぺい )の 三 ( み ) 島 ( しま ) 神社 ( じんしや )の 宮 ( みや ) 居 ( ゐ )あり 伊豆 ( いづ ) 鐵道󠄁 ( てつだう )に 乘 ( の )りかへて 一 ( ひと ) 夜 ( よ ) 泊 ( とま )らん 修善 ( しゆぜん ) 寺 ( じ )に• こゝは 御 ( ご ) 殿 ( てん ) 場 ( ば ) 夏 ( なつ )ならば われも 登 ( と ) 山 ( ざん )をこゝろみん 高 ( たか )さは 一萬 ( いちまん ) 數 ( す ) 千 ( せん ) 尺 ( じやく ) 十三州 ( じふさんしう )はたゞ 一 ( ひと ) 目 ( め )• はや上松の里過ぎぬ 結びて行かん風越の すそ野の尾花穂に出でて まねくは雪の駒が嶽• 女鳥羽の水は変われども 五層の天主今も猶 三百年のいにしえの 名残とどむる深志城• 國府津 ( こふづ )おるれば 電車 ( でんしや )あり 小田 ( をだ ) 原 ( はら ) 熱 ( あた ) 海 ( み ) 行 ( ゆ )くもよし 箱 ( はこ ) 根 ( ね ) 八 ( はち ) 里 ( り )の 山道󠄁 ( やまみち )も あれ 見 ( み )よ 雲 ( くも )の 間 ( あひだ )より• 九 ( く ) 郎判 ( らうはう ) 官 ( ぐわん ) 義經 ( よしつね )が 敵陣 ( てきぢん )めがけておとしたる 鵯越 ( ひよどりごえ )やいちのたに 皆 ( みな )この 名所 ( めいしよ )の 内 ( うち )ぞかし• 南 ( みなみ )の 風 ( かぜ )をハエと 讀 ( よ )む 南風 ( はえ ) 崎 ( ざき )すぎて 川棚 ( かはだな )の つぎは 彼 ( その ) 杵 ( き )か 松原 ( まつばら )の 松 ( まつ )ふく 風 ( かぜ )ものどかにて• 中 ( なか ) 津 ( つ )は 豐 ( ぶん ) 後 ( ご )の 繁華 ( はんくわ )の 地 ( ち ) 頼山陽 ( らいさんやう )の 筆 ( ふで )により 名 ( な )だかくなりし 耶馬 ( やば ) 溪 ( けい )を 見 ( み )るには 道 ( みち )も 遠 ( とほ )からず• 好 ( かう ) 摩 ( ま ) 川口沼 ( かはぐちぬま ) 宮 ( く ) 内 ( ない ) 中山 ( なかやま ) 小鳥谷 ( こづや ) 一 ( いち )の 戸 ( へ )と すぎゆくまゝに 變 ( かは )りゆく 土地 ( とち )の 言 ( こと ) 葉 ( ば )もおもしろや• 唱歌の曲名。 浪 ( なみ ) 江 ( え )なみうつ 稻 ( いね )の 穗 ( ほ )の 長塚 ( ながつか )すぎて 豐 ( ゆたか )なる 里 ( さと )の 富岡 ( とみをか ) 木戸 ( きど ) 廣 ( ひろ ) 野 ( の ) 廣 ( ひろ )き 海原 ( うなばら )みつゝゆく• 建見名方の神霊は 神宮寺の上社 日本第一軍神と 崇めまつるぞ尊けれ• 粟 ( あは ) 津 ( づ )の 松󠄁 ( まつ )にこと 問 ( と )へば 答 ( こた )へがほなる 風 ( かぜ )の 聲 ( こゑ ) 朝󠄁 ( あさ ) 日 ( ひ ) 將 ( しやう ) 軍 ( ぐん ) 義仲 ( よしなか )の ほろびし 深 ( ふか ) 田 ( た )はいづかたぞ• 汽 ( き ) 車 ( しや )より 逗子 ( づし )をながめつゝ はや 橫 ( よこ ) 須賀 ( すか )に 着 ( つ )きにけり 見 ( み )よ 軍港󠄁 ( ぐんかう )の 雄大 ( いうだい )を げに 東海 ( とうかい )のしづめなり• 涼しき夏の舟遊び 凍る湖上のスケートや 温泉の宿も心地よく 諏訪は四時の行楽地• おとにきゝたる 箱崎 ( はこざき )の 松 ( まつ )かあらぬか 一 ( ひと )むらの みどり 霞 ( かす )みて 見 ( み )えたるは 八 ( や ) 幡 ( はた )の 神 ( かみ )の 宮 ( みや )ならん• 大石 ( おほいし ) 良 ( よし ) 雄 ( を )が 山科 ( やましな )の その 隱家 ( かくれが )はあともなし 赤 ( あか )き 鳥 ( とり ) 居 ( ゐ )の 神 ( かみ )さびて 立 ( た )つは 伏 ( ふし ) 見 ( み )の 稻 ( い ) 荷 ( なり ) 山 ( やま )• 三 ( さん ) 家 ( け )の 中 ( なか )に 勤王 ( きんのう )の その 名知 ( なし )られし 水戸 ( みと )の 藩 ( はん ) わするな 義 ( ぎ ) 公 ( こう )が 撰 ( えら )びたる 大 ( だい ) 日 ( に ) 本 ( ほん ) 史 ( し )のその 功 ( いさを )• 末 ( すゑ )は 東 ( ひがし )の 海 ( うみ )に 入 ( い )る 阿武 ( あぶ ) 隈川 ( くまがは )も 窓 ( まど )ちかく 盡 ( つ )きぬ 唱 ( しやう ) 歌 ( か )の 聲 ( こゑ )あげて 躍 ( をど )り 來 ( きた )れるうれしさよ• [倉田喜弘] 『高取武著『増補追録歌でつづる鉄道百年』(1981・鉄道図書刊行会)』 出典 小学館 日本大百科全書 ニッポニカ 日本大百科全書 ニッポニカ について の解説. 天 ( あま )の 橋立 ( はしだて ) 三保 ( みほ )の 浦 ( うら ) この 箱崎 ( はこざき )を 取 ( と )りそへて 三松原 ( さんまつばら )とよばれたる その 名 ( な )も 千代 ( ちよ )の 春 ( はる )のいろ• 春 ( はる )さく 花 ( はな )の 藤枝 ( ふぢえだ )も すぎて 島 ( しま ) 田 ( だ )の 大 ( おほ ) 井 ( ゐ ) 川 ( がは ) むかしは 人 ( ひと )を 肩 ( かた )にのせ 渡 ( わた )りし 話 ( はなし )も 夢 ( ゆめ )のあと• 金 ( きん )と 石 ( いし )との 小 ( こ ) 金 ( がね ) 井 ( ゐ )や 石橋 ( いしばし )すぎて 秋 ( あき )の 田 ( た )を 立 ( た )つや 雀 ( すゞめ )の 宮 ( みや ) 鼓 ( つゞみ ) 宇都 ( うつの ) 宮 ( みや )にもつきにけり• 豐橋 ( とよはし )おりて 乘 ( の )る 汽 ( き ) 車 ( しや )は これぞ 豐川 ( とよかは ) 稻 ( い ) 荷 ( なり )みち 東海道󠄁 ( とうかいだう )にてすぐれたる 海 ( うみ )のながめは 蒲 ( がま ) 郡 ( ごほり )• さし出の磯の村千鳥 鳴きて過ぎ行く日下部や 石和の川に夜をこめて 鵜飼舟に棹ささむ• 世 ( よ )にも 名 ( な ) 高 ( だか )き 興 ( おき ) 津 ( つ ) 鯛󠄁 ( だひ ) 鐘 ( かね )の 音󠄁 ( ね )ひゞく 淸 ( きよ ) 見 ( み ) 寺 ( でら ) 淸 ( し ) 水 ( みづ )につゞく 江 ( え ) 尻 ( じり )より ゆけば 程 ( ほど )なき 久 ( く ) 能山 ( のうざん )• 前 ( まへ )は 海原 ( うなばら )はてもなく 外 ( と )つ 國 ( くに )までもつゞくらん あとは 鐵道一 ( てつだうひと )すぢに またゝくひまよ 青森 ( あをもり )も• 見 ( み )よや 徳川家康 ( とくがはいへやす )の おこりし 土地 ( とち )の 岡崎 ( をかざき )を 矢 ( や ) 矧 ( はぎ )の 橋 ( はし )に 殘 ( のこ )れるは 藤吉郎 ( とうきちらう )のものがたり• 初鹿野塩山向嶽寺 温泉効験いと多く 差出の磯の日下部と 螢で名高き石和町• 川を隔てて聳ゆるは 岩殿山の古城蹟 主君に叛きし奸党の 骨また朽ちて風寒し• 「鉄道唱歌」世界の童謡・唱歌無料ダウンロード 鉄道唱歌 多梅稚の「鉄道唱歌」のmidi,3gp,3g2,mp4形式の音楽ファイルが無料でダウンロードできます。 香煙細き三代の 廟に額づく人もなし 躑躅が崎の址訪えば 夏草しげく荒れ果てて• 東北一 ( とうほくいち )の 都 ( と ) 會 ( くわい )とて 其 ( その ) 名 ( な )しられし 仙臺 ( せんだい ) 市 ( し ) 伊達 ( だて ) 政宗 ( まさむね )の 築 ( きづ )きたる 城 ( しろ )に 師 ( し ) 團 ( だん )は 置 ( お )かれたり• 彼所に見ゆるは虎渓山 土岐川清く山高し 十四のトンネル絶間なく 高蔵寺勝川夢現• 鎭西一 ( ちんぜいいち )の 軍港 ( ぐんこう )と その 名 ( な )しられて 大村 ( おほむら )の 灣 ( わん )をしめたる 佐世保 ( させほ )には わが 鎭守 ( ちんじゆ ) 府 ( ふ )をおかれたり• 多治見に下車の旅人は 土岐の川辺の虎渓山 東濃一の勝境に 杖曳くことを忘るるな• 彥 ( ひこ ) 根 ( ね )に 立 ( た )てる 井伊 ( ゐい )の 城󠄀 ( しろ ) 草 ( くさ ) 津 ( つ )にひさぐ 姥 ( うば )が 餅 ( もち ) かはる 名所󠄁 ( めいしよ )も 名物 ( めいぶつ )も 旅󠄁 ( たび )の 徒 ( と ) 然 ( ぜん )のうさはらし• 眠 ( ねむ )る 間 ( ま )もなく 熊本 ( くまもと )の 町 ( まち )に 着 ( つ )きたり 我 ( わが ) 汽 ( き ) 車 ( しや )は 九州一 ( きうしういち )の 大 ( だい ) 都 ( と ) 會 ( くわい ) 人口 ( じんこう ) 五 ( ご ) 萬 ( まん ) 四 ( し ) 千 ( せん )あり• 山崎 ( やまざき )おりて 淀川 ( よどがは )を わたる 向 ( むか )ふは 男 ( をとこ ) 山 ( やま ) 行幸 ( ぎやうかう )ありし 先帝 ( せんてい )の かしこきあとぞ 忍 ( しの )ばるゝ• 鞘 ( さや )より 拔 ( ぬ )けておのづから 草 ( くさ )なぎはらひし 御 ( み ) 劒 ( つるぎ )の 御 ( み ) 威 ( いつ )は 千代 ( ちよ )に 燃 ( も )ゆる 火 ( ひ )の 燒 ( やい ) 津 ( づ )の 原 ( はら )はこゝなれや• 粂路の橋に行く人の 下車する駅は稲荷山 継は篠井停車場 信越線の連絡点• 小野の滝つせ霧はれて しぶきに虹ぞ立ちわたる 名所めぐりも束の間に須原の宿や野尻駅• 横に貫くトンネルは 日本一の大工事 一万五千呎余の 夜の闇を作りたり• 川越線の分岐点 国分寺には其の昔 聖武天皇勅願の 御寺の名残を留めたり• 阿武 ( あふ ) 隈川 ( くまがは )の 埋 ( うもれ ) 木 ( ぎ )も 仙臺平 ( せんだいひら )の 袴 ( はかま ) 地 ( ぢ )も 皆 ( みな )この 土地 ( とち )の 産物 ( さんぶつ )ぞ みてゆけこゝも 一日 ( いちにち )は• 勢田 ( せた )の 長橋 ( ながはし ) 左 ( ひだり )に 見 ( み ) ゆけば 石山 ( いしやま ) 觀 ( くわん ) 世 ( ぜ ) 音󠄁 ( おん ) 紫式 ( むらさきしき ) 部 ( ぶ )が 筆 ( ふで )のあと のこすはこゝよ 月 ( つき )の 夜 ( よ )に• 『物産唱歌』『内地旅行唱歌』『神武天皇』 さて、この唱歌シリーズは非常に売れたため、大和田建樹以外の人間が似たような作品を大量に発表し、また多くの替え歌が流行しました。
10
鉄道唱歌/訂正鉄道唱歌
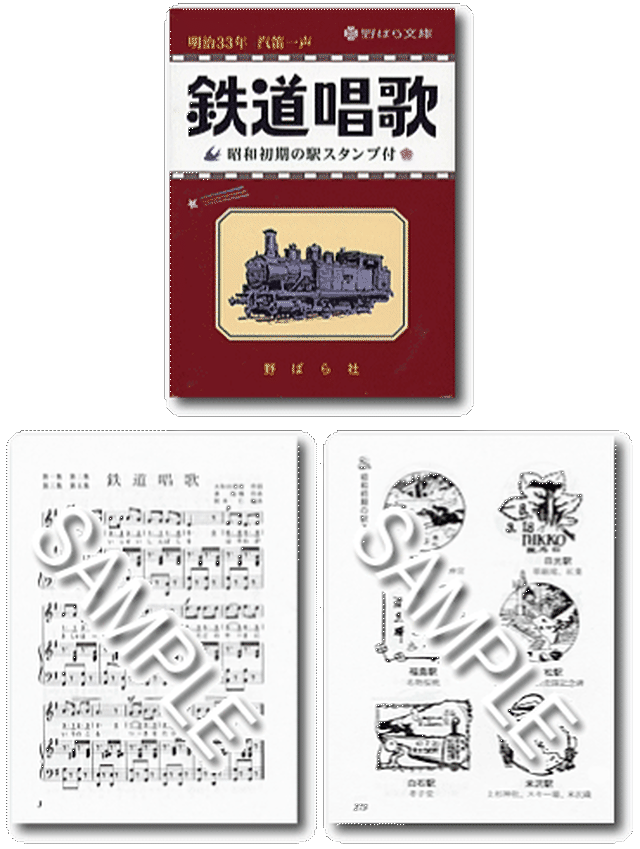
山梨県庁舞鶴城 炊煙のぼる一万戸 杖曳く園に聳ゆるは 昔ながらの天守閣• 父 ( ちゝ )やしなひし 養老 ( やうらう )の 瀧 ( たき )は 今 ( いま )なほ 大垣 ( おほがき )を 三 ( さん ) 里 ( り )へだてゝ 流 ( なが )れたり 孝 ( かう ) 子 ( し )のほまれともろともに• 五 ( ご ) 大堂 ( だいだう )を 右 ( みぎ )にして 瑞嚴 ( ずゐがん ) 寺 ( じ ) 〔 〕の 森 ( もり )ちかき 磯 ( いそ )に 船 ( ふね )は 著 ( つ )きにけり 暫 ( しば )しといふ 程 ( ほど )もなく• 赤羽 ( あかばね )すぎて 打 ( う )ちわたる 名 ( な )も 荒川 ( あらかは )の 鐵 ( てつ )の 橋 ( はし ) その 水上 ( みずかみ )は 秩 ( ちゝ ) 父 ( ぶ )より いでゝ 墨 ( すみ ) 田 ( だ )の 川 ( かは )となる• 汽 ( き ) 車 ( しや )よりおりて 旅人 ( たびびと )の まづ 見 ( み )にゆくは 諏訪 ( すは )の 山 ( やま ) 寺町 ( てらまち )すぎて 居留 ( きよりう ) 地 ( ち )に 入 ( い )ればむかしぞ 忍 ( しの )ばるゝ• 神崎 ( かんざき )よりは 乘 ( の )りかへて ゆあみに 登 ( のぼ )る 有 ( あり ) 馬 ( ま ) 山 ( やま ) 池 ( いけ ) 田 ( だ ) 伊 ( い ) 丹 ( たみ )と 名 ( な )にきゝし 酒 ( さけ )の 産 ( さん ) 地 ( ち )も 通 ( とほ )るなり• この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で 発行されておらず)、 かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、 かつ、の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においての状態にあります。 山又山を貫きて 出ずれば西條停車場 麻績の駅を過ぎて又 トンネル潜る冠着山• 積翠凝りて滴りて 玉なす水の桂川 岸千尋の断崖に かかるや猿橋虹の如• 八幡宮 ( はちまんぐう )の 石段 ( いしだん )に 立 ( た )てる 一 ( ひと ) 木 ( き )の 大 ( おほ ) 鴨脚樹 ( いてふ ) 別當 ( べつたう ) 公 ( く ) 曉 ( げう )のかくれしと 歴 ( れき ) 史 ( し )にあるはこの 蔭 ( かげ )よ• その 最 ( さい ) 期 ( ご )まで 携 ( たづさ )へし 青 ( あを ) 葉 ( ば )の 笛 ( ふえ )は 須磨 ( すま ) 寺 ( でら )に 今 ( いま )ものこりて 寳物 ( はうもつ )の 中 ( なか )にあるこそあはれなれ• 鳥 ( とり )も 翔 ( かけ )らぬ 大空 ( おほぞら )に かすむ 五 ( ご ) 重 ( ぢゆう )の 塔 ( たふ )の 影 ( かげ ) 佛法最初 ( ぶつぽふさいしよ )の 寺 ( てら )と 聞 ( き )く 四 ( し ) 天王 ( てんわう ) 寺 ( じ )はあれかとよ• 武運尽きたる武田氏が 重囲の中に陥りし 天目山は初鹿野の駅より東二里の道• 一部の古いブラウザでは、ルビが正しく見えない場合があります。 琴 ( こと )ひく 風 ( かぜ )の 濱松󠄁 ( はままつ )も 菜󠄁 ( な ) 種 ( たね )に 蝶 ( てふ )の 舞坂 ( まひさか )も うしろに 走 ( はし )る 愉󠄁 ( ゆ ) 快 ( くわい )さを うたふか 磯 ( いそ )の 波 ( なみ )の 聲 ( こゑ )• 鳥 ( とり )の 羽 ( は ) 音󠄁 ( おと )におどろきし 平󠄁 ( へい ) 家 ( け )の 話 ( はなし )は 昔 ( むかし )にて 今 ( いま )は 汽 ( き ) 車 ( しや )ゆく 富士 ( ふじ ) 川 ( かは )を 下 ( くだ )るは 身 ( み ) 延󠄁 ( のぶ )のかへり 舟 ( ぶね )• 窓 ( まど )より 近 ( ちか )く 品川 ( しながは )の 臺 ( だい ) 場 ( ば )も 見 ( み )えて 波白 ( なみしろ )き 海 ( うみ )のあなたにうすがすむ 山 ( やま )は 上 ( かづ ) 總 ( さ )か 房州 ( ばうしう )か• 都を後に見かりえて 甲州街道新宿や 又行く春に大久保の つつじの園ぞ美しき• 王 ( わう ) 子 ( じ )に 着 ( つ )きて 仰 ( あふ )ぎみる 森 ( もり )は 花 ( はな ) 見 ( み )し 飛鳥 ( あすか ) 山 ( やま ) 土器 ( かはらけ )なげて 遊 ( あそ )びたる 江戸 ( えど )の 名所 ( めいしよ )の 其一 ( そのひと )つ• 註: この文書ではが使用されています。
17
鉄道唱歌 東海道編の歌詞 全文

町 ( まち )の 名所 ( めいしよ )は 水前 ( すゐぜん ) 寺 ( じ ) 公園 ( こうゑん )きよく 池 ( いけ )ひろし 宮 ( みや )は 紅葉 ( もみぢ )の 錦 ( にしき ) 山 ( やま ) 寺 ( てら )は 法 ( ほつ ) 華 ( け )の 本妙 ( ほんめう ) 寺 ( じ )• 野邊地 ( のへぢ )の 灣 ( わん )の 左手 ( ひだりで )に 立 ( た )てる 岬 ( みさき )は 夏 ( なつ ) 泊 ( どまり ) とまらぬ 汽 ( き ) 車 ( しや )のすゝみよく 八甲 ( はつかふ ) 田 ( だ ) 山 ( さん )も 迎 ( むか )へたり• わたる 白川 ( しらかは ) 緑 ( みどり ) 川 ( がは ) 川尻 ( かはじり )ゆけば 宇土 ( うど )の 里 ( さと ) 國 ( くに )の 名 ( な )に 負 ( お )ふ 不知 ( しらぬ ) 火 ( ひ )の 見 ( み )ゆるはこゝの 海 ( うみ )と 聞 ( き )く• 行き悩みたる山道の こごしき嶺も砥の如く 三百二十余哩を 夢に過ぎけり中央線 中央線鉄道唱歌 [ ]• ふたゝびかへる 鳥栖 ( とす )の 驛 ( えき ) 線 ( せん ) 路 ( ろ )を 西 ( にし )に 乘 ( の )りかへて ゆけば 間 ( ま )もなく 佐賀 ( さが )の 町 ( まち ) 城 ( しろ )にはのこる 玉 ( たま )のあと• 手引きの岩を手末に 擎げし力折りたため 天照る神の御孫に 譲りまけしむ秋津島• 淀 ( よど )の 川舟 ( かはぶね )さをさして 下 ( くだ )りし 旅󠄁 ( たび )はむかしにて またゝくひまに 今 ( いま )はゆく 煙󠄁 ( けむり )たえせぬ 陸 ( くが )の 道󠄁 ( みち )• わが 開港 ( かいかう )を 導 ( みちび )きし 阿 ( お ) 蘭 ( らん ) 陀 ( だ ) 船 ( ぶね )のつどひたる みなとはこゝぞ 長崎 ( ながさき )ぞ 長 ( なが )くわするな 國民 ( くにたみ )よ• 千駄ヶ谷代々木新宿 中仙道は前を行き 南は品川東海道 北は赤羽奥羽線• こゝは 御 ( ご ) 殿 ( てん ) 場 ( ば ) 夏 ( なつ )ならば われも 登 ( と ) 山 ( ざん )をこゝろみん 高 ( たか )さは 一萬 ( いちまん ) 數 ( す ) 千 ( せん ) 尺 ( じやく ) 十三州 ( じふさんしう )はたゞ 一 ( ひと ) 目 ( め )• 東照宮 ( とうせうぐう )の 壯麗 ( さうれい )も 三代廟 ( さんだいべう )の 高大 ( かうたい )も みるまに 一 ( ひと ) 日日 ( ひひ )ぐらしの 陽明門 ( やうめいもん )は 是 ( これ )かとよ• 大和田建樹 おおわだたけき 作詞。 東 ( ひがし ) 那須野 ( なすの )の 青 ( あを ) 嵐 ( あらし ) ふくや 黒磯黒 ( くろいそくろ ) 田 ( た ) 原 ( はら ) こゝは 何 ( いづ )くと 白河 ( しらかは )の 城 ( しろ )の 夕 ( ゆふ ) 日 ( ひ )は 影赤 ( かげあか )し• 汽 ( き ) 車 ( しや )に 乘 ( の )りても 松島 ( まつしま )の 話 ( はなし )かしまし 鹿 ( か ) 島臺 ( しまだい ) 小牛田 ( こゞた )は 神 ( かみ )の 宮 ( みや )ちかく 新 ( につ ) 田 ( た )は 沼 ( ぬま )のけしきよし• そして、あまりの人気に、その後、作者自ら膨大な改訂版や亜種を出していくのです。 作曲:福山直秋• 曲を取得するまでに20秒程度かかります。
14
鉄道唱歌/山陽・九州篇

次は甲府の城の跡 山岳四面に重畳し 甲州一の大都会 山梨県庁ここに在り• 辰野小野も通り過ぎ 伊那谷渉りて塩尻は 茫たる平野にステーション 篠井線の分岐点• 末 ( すゑ )は 銚 ( てう ) 子 ( し )の 海 ( うみ )に 入 ( い )る 坂東 ( ばんどう ) 太 ( た ) 郎 ( らう )の 名 ( な )も 高 ( たか )し みよや 白 ( しら ) 帆 ( ほ )の 絶 ( たえ ) 間 ( ま )なく のぼればくだる 賑 ( にぎはひ )を• 汽 ( き ) 笛 ( てき )ならして 客 ( きやく )を 待 ( ま )つ 汽 ( き ) 船 ( せん )に 乘 ( の )れば 十 ( じふ ) 五 ( ご ) 分 ( ふん ) 早 ( はや )くもこゝぞ 市 ( いち ) 杵 ( き ) 島 ( しま ) 姫 ( ひめ )のまします 宮 ( みや )どころ• 福島町は御料局 木曾の支庁のある処 水を隔てて両岸に 連なる家は一千戸• 岩國川 ( いはくにがは )の 水上 ( みなかみ )に かゝれる 橋 ( はし )は 算盤 ( そろばん )の 玉 ( たま )をならべし 如 ( ごと )くにて 錦帶橋 ( きんたいけう )と 名 ( な )づけたり• 日清戰爭 ( につしんせんさう )はじまりて かたじけなくも 大君 ( おほきみ )の 御 ( み ) 旗 ( はた )を 進 ( すゝ )めたまひたる 大本營 ( だいほんえい )のありし 土地 ( とち )• 曲は常に2パターンありますが、有名なのは上の方 もともとこの歌を作った出版社が倒産し、版権を譲り受けたのが楽器商の三木佐吉でした。
鉄道唱歌・完全版

むかしながらの 山 ( やま ) 櫻 ( ざくら ) にほふところや 志賀 ( しが )の 里 ( さと ) 都 ( みやこ )のあとは 知 ( し )らねども 逢坂山 ( あふさかやま )はそのまゝに• おくり 迎 ( むか )ふる 程 ( ほど )もなく 茨木 ( いばらき ) 吹 ( すひ ) 田 ( た )うちすぎて はや 大阪 ( おほさか )につきにけり 梅 ( うめ ) 田 ( だ )はわれをむかへたり• 夏 ( なつ )はすゞみの 四 ( し ) 條橋 ( でうばし ) 冬󠄀 ( ふゆ )は 雪󠄁 ( ゆき ) 見 ( み )の 銀閣 ( ぎんかく ) 寺 ( じ ) 櫻 ( さくら )は 春 ( はる )の 嵯峨御 ( さがお ) 室 ( むろ ) 紅 ( もみ ) 葉 ( ぢ )は 秋 ( あき )の 高 ( たか ) 雄 ( を ) 山 ( さん )• 表記は歴史的仮名遣とし、漢字制限はJIS X 0208に文字が収録されていれば元の漢字をそのまま使った。 瀧内さんに教えていただきました。